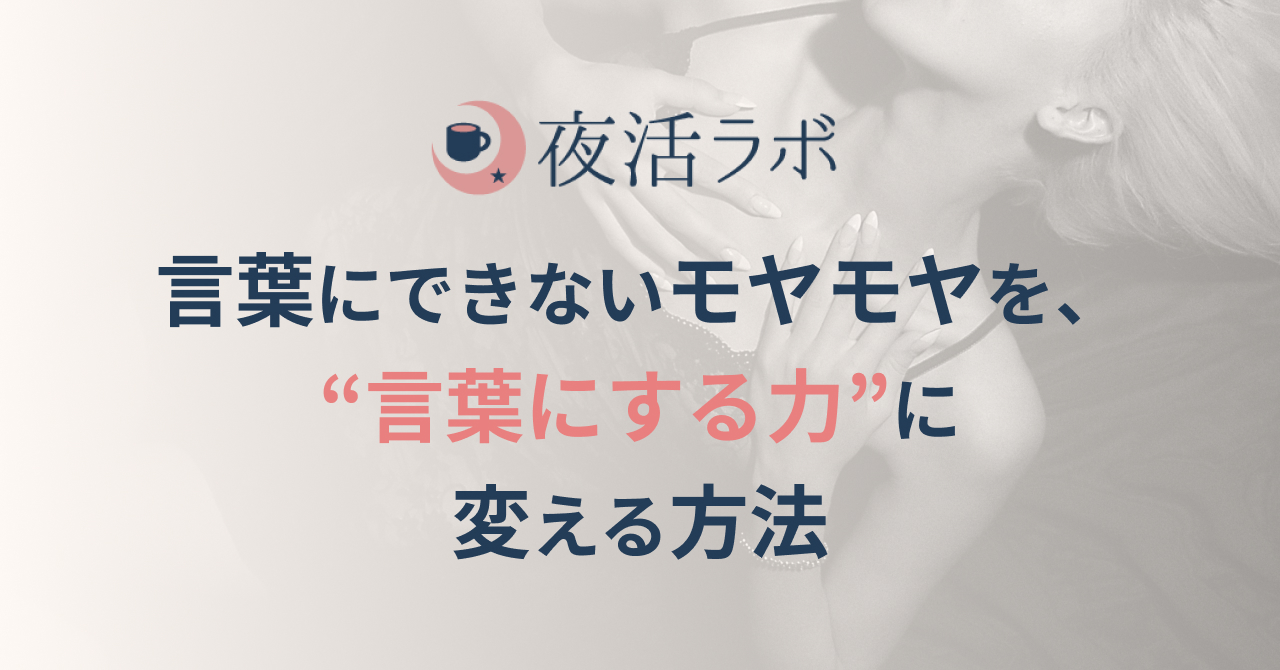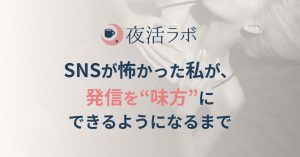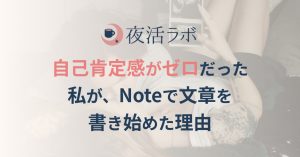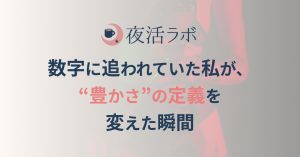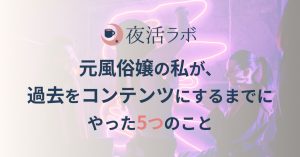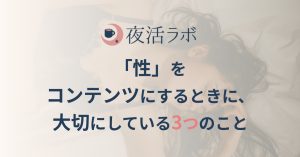「なんかモヤモヤする…」「言葉にできないけど、ずっと胸がざわついている」
そんな感情を抱えたまま、夜が来るのが怖かった。静けさの中で心だけがざわめき、自分を責める声だけが大きくなる。SNSを開いても、誰かの幸せそうな投稿が突き刺さる。見ないほうがいいとわかっていても、やめられなかった。
私もかつて、そうだった。何かがつらい。だけど、それが何かがわからない。その「わからなさ」が、私をいちばん苦しめた。この記事では、そんな“言葉にならない感情”と、どう向き合い、どう「言葉にしてきたか」の道のりを、私自身の体験からお話ししていきます。
なぜ、言葉にできない感情は苦しいのか?
感情は、名前を与えられたときに初めて輪郭を持ちます。
「悲しい」「悔しい」「寂しい」「虚しい」
そうラベルが貼られることで、ようやく自分の中で整理ができ、向き合うことができる。けれど、「なんとなくつらい」「なにがイヤなのかわからない」といった“名前のない感情”は、自分の中でぐるぐると回り続け、出口を見つけることができない。
私が一番苦しかったのは、風俗の仕事をしていたとき。誰にも言えない仕事、バレてはいけない過去、自分でも受け入れきれていない選択。帰り道、電車の窓に映る自分が、誰よりも空っぽに見えた。
「私、何してるんだろう」
その思いを誰かに言葉にして伝えることができたら、きっと少しは楽だった。でも私は、自分自身にさえ、その感情を説明できなかった。
「書くこと」が唯一、自分を助けた
夜の仕事をしていたころ、私は毎日メモ帳アプリを開いて、意味のない文章を書き綴っていた。
「死にたい」とも「つらい」とも、最初は書けなかった。でも、「帰りたくない」「疲れた」そんな言葉を打ち込んでいると、不思議と涙が出た。誰にも見せない、誰にも読まれない、ただのひとり言。それでも、言葉にして外に出すことで、少しだけ自分が癒されていく感覚があった。
そしてある日、SNSに少しだけ気持ちを書いてみた。「なんか、泣きたくなる夜。」たったそれだけの言葉に、誰かが共感してくれた。「わかる」「私もそう」そう言ってくれる人がいることが、私を少しずつ救ってくれた。
「誰かに届く」言葉じゃなくていい
最初から、誰かの心を打つような文章を書こうとしなくていい。
私は最初、うまく書こうとすればするほど、筆が止まった。「価値ある投稿をしなきゃ」「誰かに読まれなきゃ意味がない」そんなふうに思っていたけど、それが一番、自分を苦しめていた。
でもあるとき、ふと思った。「これは、私のために書くものなんだ」
そう思えたときから、書くことが怖くなくなった。正確な文法じゃなくても、キレイな言葉じゃなくても、自分が「こう思った」と表現すること、それ自体に価値があるんだと、やっとわかった。
自分を守るために「書かない」選択もOK
すべてのことを言葉にする必要はないし、すべての感情を人に見せる必要もない。
言葉にすることで癒されることもあれば、逆に心が傷つくこともある。私は何度か、書いたことを後悔したこともあった。勇気を出して出した言葉に、誰かが無神経な反応を返してきたとき。見られたくなかった人に、過去を知られたとき。
そんなとき、自分を責めないで。「書くこと」には力がある。でも、それは自分を守るための力でもあってほしい。だからこそ、書かないという選択にも、ちゃんと意味がある。
「言葉にする力」は、誰の中にもある
今、私はこうしてNoteやブログで文章を書いています。昔の私からしたら、考えられないことでした。
でも今なら、はっきり言えます。
「言葉にできなかった私だからこそ、伝えられることがある」
文章を書く力なんてなかった。タイピングも遅かったし、何を書いても稚拙に思えた。でも、続けているうちに少しずつ「自分の声」が見えてきた。
誰かのためにじゃなく、自分のために。誰かに見せるためじゃなく、自分の心を整理するために。そうやって続けた書く習慣が、今の私を救ってくれた。
おわりに:あなたにも、書ける。
言葉にできない気持ち、ありますよね。大丈夫。それは、あなたが感受性豊かで、たくさんのことを感じ取っている証拠です。
無理に説明しようとしなくていい。まずは一言、ノートでもスマホでもいい。「今日は疲れた」でも「泣きそう」でも、それだけで十分。
書くことで、自分の感情を「他人事」のように眺められるようになります。
そして気がついたら、あなたの中にあった“ぐちゃぐちゃの塊”が、少しだけ輪郭を持ちはじめているかもしれません。
もし、誰かに話せないことがあるなら、まずは「自分のために」書いてみてください。
あなたにも、必ず「言葉にする力」があります。